自己破産をすると、一生「破産者」のレッテルを貼られ、人生を台無しにしてしまう印象があります。これは間違った印象であり、自己破産の選択肢を選ばずに自殺という選択肢を選んでしまうケースもあります。自己破産はゼロからすべてをやり直すための選択肢です。今回は「自己破産とは?」について紹介します。
目次
債務整理と自己破産

借金は返済をしなければ増えていきます。また、借金を返済するために別の貸金業者からお金を借りるという方法は、現在利用できません。仮にできたとしても多重債務に陥り、最終的には借金の額が膨れあがってしまいます。つまり、意味がありません。
借金を減らす方法として現実的なものは、「債務整理」です。
[aside type=”boader”]
債務整理とは、
- 任意整理
- 特定調停
- 民事再生(個人再生)
- 自己破産
これらがあり、自己破産は債務整理の1つの方法です。[/aside]
そして、任意整理、特定調停、民事再生(個人再生)の3つの債務整理については、借金の額を減額することが主な目的となります。借金の額を減額して、返済スケジュールを組んで3年程度で全額返済をしなければなりません。
3つの債務整理を選択した方がいい人については、持ち家や高額な財産を処分したくない上、完済するまで安定した収入がある場合は利用することいいでしょう。
[aside type=”boader”] 「自己破産」は債務整理の最後の手段です。[/aside]自己破産について
自己破産をするためには裁判所へ申立てる必要があります。
申立人(債務者)の収入や借金の額を裁判所が考慮して、借金の支払い能力があるのかないのかを判断します。たとえば、年収が50万円で借金が1,000万円あるとすれば、借金の返済は不可能なので「支払不能状態」といいます。
[aside type=”boader”] 裁判所が支払不能状態と判断したら、自己破産の手続きが開始できます。[/aside]支払不能状態と裁判所が判断すると「破産手続開始決定」が下り、その後、「免責許可の決定」を受けることで自己破産が完了しますが、そもそも、支払不能状態と判断されないと破産手続開始決定は下りません。
自己破産を選択した場合、持ち家や高額な財産を処分しなければならないというデメリットがありますが、現在、抱えている借金を免責することが可能です
[aside type=”warning”]ただし、滞納している税金など一部の借金については免責されませんが、その他の借金問題は自己破産をすることですべて解決します。[/aside]支払不能状態とは?

自己破産をするためには、「支払不能状態」と認められる必要があります。ただ、支払不能状態には明確な基準がありませんので注意が必要です。さらに、支払不能状態は、債務者の職業・収入・資産状態・社会的地位や債務者の年齢・性別・信用・労力・職業などを総合的かつ客観的に借金の返済能力がないと裁判所が判断をします。
支払不能状態の大まかな基準としてはこのようなものがあります。
[aside type=”boader”]
- 履行期に借金を返済できない状態が継続的に続いている
- 履行期にあたる債務が3~5年で完済する見込みがない
- 借金額が年収の1.5倍以上ある
- 財産があってもすぐに換金して現金化することができない
逆に、財産があったとしてもその財産が現金化することが難しいものでしたら、支払不能状態となります。さらに、今月、たまたま20万円の借金があり返済することができない場合も支払不能状態とは認められません。
自己破産の進め方
支払不能状態である
継続的、そして客観的に借金の返済能力が欠乏していれば、支払不能状態と裁判所から判断されます。
仮に認められない場合は、自己破産以外の債務整理から借金の返済方法を選ぶことになるでしょう。
相談
自己破産については、他の債務整理の方法とは異なり、債務者の独力でおこなうことが可能です。ただし、ある程度の財産を持っている債務者の場合は弁護士に依頼をして自己破産の手続きを進めた方が比較的簡単でいいでしょう。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]財産が無い場合であっても、保証人とのトラブルに発展する可能性がありますので、弁護士や司法書士に助力を仰ぐことをおすすめします。[/voice]弁護士の方が費用は高くなりますが、弁護士会・法テラスなどの無料法律相談所などが便利です。また、弁護士に依頼をしますと「受任通知および債権者調査への協力願い」を債権者へ発送します。これを受け取って以降、債権者は借金の取り立てをすることができなくなります。
[aside type=”warning”]現在はあまりその姿を見なくなりましたが、「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といった借金整理をうたう悪徳業者も存在します。これらの業者を利用した場合、借金の額が増えることはあっても減ることはないので注意しましょう。[/aside]破産手続開始の申立書の提出
支払不能状態である申立人(債務者)は、住所地の管轄する地方裁判所に書面で「破産手続開始の申立書」を提出します。
[aside type=”boader”] 住民票がある地方裁判所ではなく、現在住んでいる地域を管轄している地方裁判所に提出する必要がありますので注意をしてください。[/aside]書面審理と審尋(しんじん)
通常は申立人が提出した書面や書類を審理する書面審理や、裁判官が破産申立人に破産手続き開始の申立て内容について直接口頭で質問をする「審尋(しんじん)」があります。
基本的に申立書に書いた内容を尋ねられます。
破産手続開始決定
[aside type=”boader”] 破産審尋から1週間~1ヶ月後程度で、申立人(債務者)が支払不能状態であると裁判所が判断をすれば、「破産手続開始決定」が下ります。破産手続開始決定とは、裁判所が、破産手続きの開始を宣言する決定を出すことです。[/aside]破産法が改正される前は「破産宣告」と呼ばれていました。破産宣告と破産手続開始決定は同じ意味で説明されています。
東京地方裁判所の場合は、弁護士が債務者から受任され、代わりに申立てることで申立日に弁護士と裁判官が面接をおこない、破産手続開始・同時廃止決定が即日おこなわれる即時面接手続がおこなわれています。
破産手続開始決定の際は、運転免許証や健康保険証といった身分証明書と認印を持って、破産手続開始の決定書を裁判所へ取りに行きます。これを持って申立人(債務者)は破産者となります。
[aside type=”boader”] 破産手続開始決定されたと「官報」により公告し、債権者へ知らせます。この時点で、債権者は破産者から取立てをすることができなくなります。[/aside]同時廃止事件と管財事件
同時廃止事件
通常、裁判所は破産手続開始決定をおこなうと同時に、破産管財人を選任し、管財人が破産者のすべての財産を調査・管理します。そして、換金できそうな財産はお金へ替え、債権者へ分配することになります。
[aside type=”boader”] 破産者の財産が少なく、これを換金しても破産手続の費用に明らかに満たない場合(原則として財産が20万円以下)は、裁判所は破産管財人の選任を行なわず、破産手続開始と同時に破産手続き終了を決定します。[/aside]これが「同時廃止事件」となります。この場合、債務者の財産の管理・換金等の手続きはおこなわれず、破産手続は終了となり、次の「免責手続」に入ります。
同時廃止事件にしたい場合、破産手続開始日の申立書に同時廃止事件にしたい旨を記載する必要があります。
管財事件
[aside type=”boader”] 管財事件は、破産債務者に破産手続費用を支出するに足りる一定の財産があるときは、裁判所が破産管財人を選任して管財人が破産債務者のすべての財産を調査・管理し破産手続開始の時点から破産者の財産は「破産財団」と呼ばれ、勝手に処分できなくなります。[/aside]破産財団になるものは、退職金の一部や家財道具、不動産などが破産財団となり、現金化できる破産財団などは裁判所の監督のもと管財人が売却して換金します。その後、すべての債権者に対して、債権額に比例した割合で公平に配当(分配)が行われます。
このため、債権者は個別に債権を利用して破産債務者の家財道具などを差し押さることはできなくなります。また、破産手続開始前に家財道具へ行った差押さえの効力は失効されます。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]破産手続費用を支出するに足りる一定の財産とは、生活費等控除後の財産が原則として20万円以上あれば行なわれます。おこなうためには、予納金を納める必要があります。予納金の額は裁判所の窓口での確認が一番正確でしょう。[/voice]管財人が調査をおこない配当すべき財産が無い場合は、異時廃止といい、破産手続きは途中で終了です。また、東京地方裁判所の場合は少額管財事件手続きがあります。
管財事件の場合、破産手続きは、破産手続開始日から半年~1年程度の期間がかかります。換価が困難な財産がある場合、処分に1年以上かかるケースもあります。特に家などの不動産は競売などにかけられますので、売却されるまでは居住可能です。
[aside type=”warning”]また、破産管財人ですが、法律関係の処理が必要なので法律の専門家である弁護士が選任されます。そのため、選任された破産管財人に支払う報酬などが別途必要になるので注意しましょう。[/aside]免責許可の手続き
破産開始決定が下っても、借金の帳消しにはなりません。借金を帳消しにするためには、さらに「免責許可」を得る必要があります。
[aside type=”boader”] この「免責」とは、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の借金について、裁判より、借金の返済責任を免除することです。債務者が申立てた自己破産の場合は、破産手続開始の申立により免責許可の申立をしたとみなされます。そのため、あらためて「免責許可の申立」をする必要はありません。[/aside]免責についての事情を裁判官が尋ねるため免責審尋が開かれます。免責審尋を受けるためには裁判所へ出頭して、免責審尋を受けます。その後、1週間~10日程度で「免責許可」もしくは「免責不許可」決定がされます。
免責許可決定が下れば、破産者の借金は帳消しになります。免責許可が決定した場合、裁判所より破産者および債権者に通知が、ただちになされます。異議などがなければ免責が確定します。
免責不許可事由
免責の許可がなければ借金は帳消しになりません。裁判所が免責を認めない免責不許可事由というものがあります。ただ、免責不許可事由がある場合でも事情を考慮して、免責許可になる場合もあります。これを「裁量免責」と呼びます。
免責不許可事由は下記のものがあります。
[aside type=”warning”]
- ギャンブルなどの浪費行為がある場合
- 破産をする前に特定の債権者にのみ返済をした場合
- 換金行為をした場合
- 名義を偽りクレジットカードの利用や借金をした場合
- 裁判所により定められた出頭命令などを無視するなど不誠実な態度が目立つ場合
復権

自己破産開始手続の申立てをすると破産者となります。
破産者となると本籍地の市区町村役場にある「破産者名簿」に名前が記載されます。名前が記載されますが、第三者が「破産者名簿」を勝手に閲覧することは不可能なので、いつの間にか破産者であることが周囲にばれる可能性はありません。
[aside type=”boader”]
免責許可が確定しますと「復権」の効力が発揮します。「復権」の効果が発揮されます。復権とは、破産者となったことで生じる不利益をなくし、破産前と同じ状態に戻ることを指します。また、「破産者名簿」から指名が抹消されます。
さらに、破産者では、弁護士、会計士などの一部の資格を使用しての仕事をおこなうことができなくなったり、警備員や保険外交員などの一部の仕事などに就けなくなりますが、復権をすることでこの職業の不利益はなくなります。もちろんですが、破産者になったからといって仕事をクビにされるという不利益を被ることはありません。[/aside]
破産手続開始の申込みから復権をするまでに、同時廃止事件の場合は3カ月~半年間で破産手続は終了して復権をすることができます。復権をしてしまえば、破産者ではありませんので、一般人と同じように生活することが可能です。
自己破産のメリット・デメリット
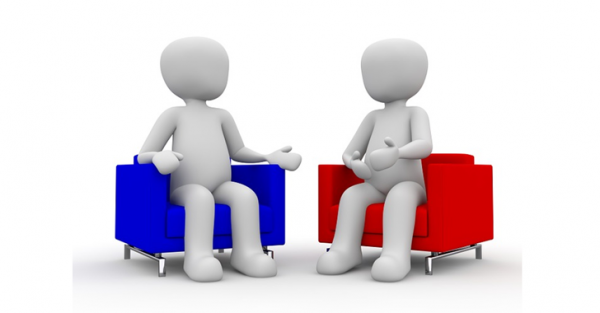
自己破産のメリット
[aside type=”boader”]自己破産のメリットは下記の通りです。- 借金が免除される(滞納税金等は免除されない)
- 支払不能状態なら誰でも手続きをすることが可能
- 取立てなどを止めることができる
- ある程度の財産を手元に残すことができる
- 自己破産を理由に職場で不利益を被ることはない
また、金融機関からの取立てを法的に止めることが可能です。さらに、高額な財産は処分しなければなりませんが、ある程度の現金を手元に残すことができます。自己破産をしたからといって無一文になるまで財産をむしり取られることはないので、心配する必要はありません。
[aside type=”boader”] 会社法の改正以前は、株式会社の取締役や監査役、合名会社・合資会社の社員は自己破産を理由に退任・退社させることが可能でしたが、現在は自己破産を理由に退任・退社させることは禁止されています。自己破産を理由に現在勤めている会社で不利益を被ることはないので安心してください。[/aside]自己破産のデメリット
自己破産のデメリットは、下記の通りです。
[aside type=”boader”]
- 7年間は再度自己破産ができない
- 破産者は公法・私法上の資格制限を受ける
- 官報に名前が載る
- 信用情報機関のブラックリストに名前が載り、5年~10年は借金ができない
- 管財事件の手続き中は、生活に制約がつく
- 自己破産の申立ては有料である
7年間は再度自己破産ができない
一度、自己破産をして免責許可決定を受けた場合、原則として7年間は再度の免責許可決定を受けることはできなくなります。
[aside type=”boader”] つまり、7年間は自己破産の恩恵を受けることができなくなりますが、信用情報機関のブラックリストに登録をされていますので、クレジットカードやキャッシュカード、ローンの審査に通るが難しいので、そこまで大きなデメリットというわけではありません。[/aside]公法・私法上の資格制限を受ける
これは、自己破産の手続き中、破産者のときに受ける不利益であり、免責許可決定を受けて復権をしてしまえば、資格の制限はなくなります。
破産者は下記の資格を利用した仕事ができません。
[aside type=”boader”]
- 公法上の資格の制限:弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引業者
- 私法上の資格の制限:後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者
官報に名前が載る
破産手続開始決定を受けて破産者になったり、免責許可決定などを受けて復権をしたりした場合、「官報」という政府が一般国民に知らせる事項を編集し、毎日刊行する公告文書に名前が掲載されます。
[aside type=”boader”] 官報に小まめに目を通している人など極めて少ないといえます。また、破産者の名前が官報に載っていることを知っている人口の方が少なくなります。つまり、官報に名前が載ったところで気が付く人物は滅多にいないわけです。[/aside]信用情報機関のブラックリストに名前が載り、5年~10年は借金ができない
自己破産とは、金融事故です。そのため、5年~10年はローンやクレジットカードの申込み、キャッシングの審査などの審査に通りにくくなります。つまり、借金をすることが難しくなるのです。
[aside type=”boader”] 5年~10年経過すればブラックリストから名前が抹消されますので、以降は不利益を被ることはありません。[/aside]管財事件の手続き中は、生活に制約がつく
破産手続開始から免責許可決定が下りるまでの間は、破産者になります。特に管財事件の破産者になると下記の制約がつきます。
[aside type=”warning”]
- 財産の管理処分権の喪失
- 居住の制限
- 通信秘密の制限
- 逃げたり、財産を隠したりする素振りがあると拘束・監視される
自己破産は有料である
破産手続開始・免責許可の申立手続費用は、同時廃止事件の場合原則として下記の通りです。
[aside type=”boader”]
- 官報公告掲載費用:現金10,584円
- 破産手続開始・免責許可申立手続費用の収入印紙代:1,500円
- 書類の送付費用などの切手代金:500円切手×2枚、82円切手×債権者数+6枚、52円切手1枚、20円切手1枚
まとめ
自己破産をすると、滞納税金などを除いて借金をすべて帳消しにすることが可能です。
自己破産をするためには、支払不能状態であると裁判所に判断された上、破産手続開始を経て、免責許可決定を受けることで完了します。
一見するとデメリットが多いように見えますが、普通に生活をしているうえでは特別、デメリットを感じることはありません。むしろ、借金の問題で頭を抱える方が精神衛生的に悪いといえます。
[aside type=”boader”] 現在ある借金が、客観的に返済不能だと思った場合、自己破産というのは非常に有効な手です。自己破産をした後10年程度は、新しく借金をすることができなくなりますが、経済基盤を立て直す時期と考えれば、この期間は有用でしょう。[/aside]

