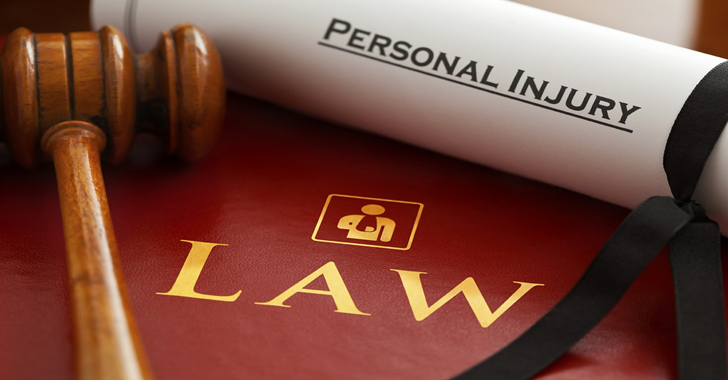自己破産は債務整理の方法では、最後の手段である法的手続きです。しかし、自己破産をすることができないケースが存在します。たとえば、借金の返済能力があるにも関わらず自己破産をすることは原則不可能です。なぜなら、「支払不能状態」ではないからです。
このほかにも自己破産が認められないケースはあります。今回は自己破産ができない場合はどのような場合なのか紹介をしていきます。
目次
自己破産ができないケースがある?

自己破産は、債務整理の最後の手段です。法的に借金を帳消しにするものですが、誰でも利用することができてしまっては、貸し倒れを前提にしてお金を借りる人も出てきてしまうわけです。そのため、自己破産ができないケースは存在します。
[aside type=”boader”] 自己破産ができないケースとしては、- 借金の額がそれほど多くないケース
- 自己破産費用を用意できないケース
- 免責不許可事由が存在するケース
- 自己破産を選択するのが難しい職業についているケース
この4つのケースが考えられます。[/aside]
法律上、自己破産ができないケースというのは非常に稀です。たとえば、2番目の免責不許可事由に該当していても、本当に悪質でなければ最終的には裁量免責が認められます。
たとえば、免責不許可事由の1つであるギャンブルや浪費が原因の自己破産であっても、実務上では、裁量免責において大半の人が免責を受け借金が帳消しとなっています。
財産を意図的に隠したり、破産管財人という裁判所が選任した弁護士に非協力的だったりしない限り、よほどのことがなければ自己破産をすることができないと考えるのは早計です。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]つまり、免責不許可事由に該当=自己破産ができないというわけではないのです。[/voice]借金の額がそれほど多くないケース

自己破産については、債務整理の最後の砦になります。そして、支払い不能状態の債務者の救済するための法的な手段です。そのため、「借金が支払い不能」と認められない限り、自己破産をすることはできません。
これは破産法15条、30条に規定されています。
破産法15条では、(破産手続開始の原因)
1項、 債務者が支払い不能にあるときは、裁判所は第30条第1の規定に基づき、申立てにより決定で破産手続を開始する。
2項、 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。破産法30条では、(破産手続開始の決定)
裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
また、破産法2条にて「支払不能」について定義されています。
破産法2条では、(支払不能の定義)
この法律において「支払不能」とは、債務者が支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。
このように定義されています。
[aside type=”boader”] つまり、- すでに弁済期にある借金である
- 一般的かつ継続的に返済ができない状態
この2つの要件がそろえば支払不能状態となります。[/aside]
仮に莫大な額に借金が膨れ上がったとしても、まだ返済期日が到来していない場合、自己破産をすることはできません。また、一時的に資金繰りに困っている場合、一部の債権者のみ返済をすることができない場合も、自己破産が認められない可能性があります。
そのため、リポ払いで数百万円の借金を抱えていても、毎月きちんと継続的に返済をしており、滞納をしていないのであれば、支払不能状態とは判断はされません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]このような場合は、弁護士へ自己破産の相談・依頼をおこない受任通知を送付してもらえば、その時点から返済を停止することになります。弁護士が介入して借金の返済を停止させてしまえば、破産法15条において支払不能と推定されるのです。結果として、自己破産の手続き上、問題とはなりません。[/voice]3年以内に返済可能であれば自己破産ができない
[aside type=”boader”] 現時点の借入残高を、利息抜きで分割払いにしてもらい、2年~3年間で返済をすることが可能なのであれば、返済することが可能なので「支払不能状態」とは認められない可能性があります。[/aside]たとえば、任意整理の場合、将来発生する利息をカットして、元本を3年以内に返済をするという交渉をおこない和解をします。つまり、任意整理や特定調停を利用して、返済期間のリスケジュールと利息カットをすることで、債務者が返済可能なのであれば自己破産をする必要性というのはありません。
一般的には3年で返済をすることができれば、自己破産は却下されます。1年~2年で返済可能なら高い確率で却下されるでしょう。そして、3年を超える場合では債務者の個別の事情や裁判官の考え方に左右されてしまいます。
[aside type=”boader”] また、借金が100万円以下の場合は自己破産をすることができないといわれています。これは、一般的な家庭では「毎月3万円くらいなら返済ができるだろう」という前提からくるものです。毎月3万円を元本の返済に回せば108万円未満であれば3年で完済できます。[/aside]そのため、毎月3万円を返済するのが難しい貧困家庭や母子家庭で収入が少ない場合、そして著しく生活が困窮している場合では100万円未満であったとしても自己破産をすることが可能です。
自己破産の費用を用意することができない場合、自己破産ができない

破産手続の予納金は、同時廃止事件であれば1万円~1万5000円程度かかります。同時廃止事件の場合なら予納金を支払うことができないということはないでしょう。しかし、管財事件・少額管財事件になった場合、最低20万円~50万円の予納金が必要になります。
つまり、管財事件・少額管財事件の場合は予納金を用意することができないゆえに、自己破産ができない、というケースが実際にあります。
予納金は原則、現金一括払いですが、東京地裁の場合は4回まで分割払いを認めています。また、法テラスの「立替金制度」を利用などもあります。
[aside type=”boader”] 現実問題、弁護士へ依頼をすることで受任通知が各債権者へ送付されます。受任通知を受け取った債権者は、借金の取立や督促などを貸金業法で禁止されてしまうのでできません。つまり、この間、借金の支払義務がなくなります。そのため、半年程度かけて予納金を積み立てて準備をして申立てをするという方法が現実的です。[/aside]一定額以上の財産を持っていると、管財事件・少額管財事件となります。しかし、一切財産がないのであれば同時廃止事件になります。そして、一般的には同時廃止事件の方が多く、そこまで心配する問題でもなければ、手元にまとまったお金がないからといって自己破産を諦める必要もありません。
免責不許可事由が存在し、破産手続で止まってしまう
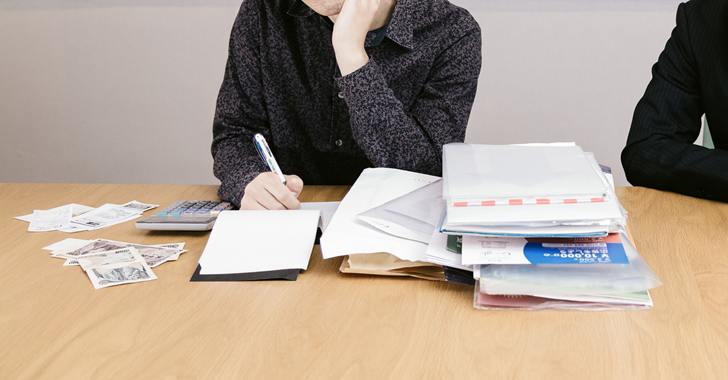
破産手続とは、債権者の財産を清算して債権者に配当する手続きを意味します。免責許可制度とは別です。また、破産手続をおこなうことで、借金の返済義務がなくなるということは、破産手続に協力をした破産者にのみにしか与えられるものではありません。
[aside] そのため、破産者が不誠実な対応をしている場合、破産手続き自体は開始されるものの、免責許可は認められない」という風になってしまいます。不誠実な対応をする破産者について定めたものが、破産法における「免責不許可事由」です。[/aside]免責不許可事由とは?
[aside type=”boader”] 免責不許可事由を簡単に説明した場合、下記のようなものになります。- 自己破産をする前に財産を隠すなど、わざと減らした場合
- 闇金やクレジットカードで購入したものを廉価で換金した場合
- ギャンブルやFXなどの投資(射幸行為)で借金を作った場合
- 買い物や女遊びなどの浪費で借金をした場合
- 自己破産の直前に嘘をついてお金を借りた場合
- 自己破産してから7年以内に自己破産をする場合
- 裁判所に嘘の説明をしたり、隠し事をしたりした場合
このような免責不許可事由があります。免責不許可事由、たとえばギャンブルで自己破産を選択する場合、100%自己破産ができないというわけではありません。[/aside]
免責不許可事由があったとしても、自己破産で免責許可を得ることも可能です。
破産法では、免責不許可事由がある場合、担当の裁判官が自らの権限で免責を許可することが認められています。これが、裁量免責というものです。
[aside type=”boader”] そのため、ギャンブルで借金を作っても、破産者に反省の色が見られる場合は、免責が下りるケースが一般的です。ギャンブルで破産をする人は非常に多くいます。そのような人々全員が免責不許可になった場合、自己破産は法的な救済措置として機能しなくなってしまいます。[/aside]自己破産でも非免責権があるものは帳消しにできない
自己破産をすることができないものとして、
[aside type=”boader”]
- 交通事故やその他の損害賠償請求
- 養育費の支払い義務
- 未払いの税金
これらは、法律上「非免責債権」と呼ばれます。[/aside]
これらの債権については、自己破産をしても支払義務は残ります。
ここで、勘違いしてしまう方が多いのですが非免責債権がある場合は自己破産をすることができないというものです。非免責債権があったとしても自己破産は可能です。また、非免責債権があるからといって免責許可に影響を与えることもありません。
非免責債権は、免責許可が下った後でも非免責債権の支払義務が残り続けるだけです。
そのため、非免責債権があるから、免責許可を得ることができないのでは? という心配は不要です。破産手続の中で非免責債権が影響を与えることはなく、自己破産ができなくなるということもありません。
自己破産を実質的に選択することができない

法律上は自己破産をすることができる、つまり、支払不能状態であり、免責不許可事由がない場合でも、自己破産を選択することができない、もしくはしたくないケースが存在します。
[aside type=”boader”] 自己破産をした場合、免責許可を受けるまで「破産者」となります。破産者になると職業制限がかけられます。つまり職業制限を受けてしまう職業についている人は自己破産をしたくても自己破産を選択することができないというわけです。[/aside]自己破産による職業制限について
[aside type=”boader”]- 公認会計士
- 宅地建物取引士
- 弁護士
- 司法書士
- 不動産鑑定士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 証券外務員
- 質屋
- 調教師・騎手
- 警備員
などの職業についている場合、自己破産をすると法律上の欠格事由となります。欠格事由になりますと、自己破産の手続きが終了するまでの間、その仕事につくことができません。[/aside]
資格制限について、どのくらい厳しいのかといいますと、職業により異なります。
たとえば、宅地建物取引士のような必ず資格の登録が取り消される場合(復権後元に戻ります)、保険外務員のように報告義務がなく、取消も監督庁の任意のため、実際にはほとんど取り消されない場合もあります。
資格制限が厳しい場合は、破産者の間は別の職務をおこない、復権を果たしたらもとの職務に戻る。もしくは自己破産と同時に退職扱いになり、復権後再就職をするというケースもあります。
本当に自己破産をすることができない場合

- 債務整理(任意整理・個人再生)
- 借金の消滅時効まで待つ
この2つの方法ですが、現実的なのは債務整理です。
別の債務整理(任意整理・個人再生)
任意整理
任意整理は、法律で定められた手続きではなく弁護士と債権者が私的に交渉をおこない和解を目指すものです。裁判所の介入もなく敷居が低いメリットがあります。
免責不許可事由のようなものもなく、任意整理が現実的にはもっとも利用される方法です。
[aside type=”boader”] しかし、任意整理では将来利息のカット、遅延損害金のカット、返済期間のリスケジュールができればいい方であり、借金の減額効果についてはそこまで高くはありません。そのため、多額な借金がある場合は、利用しても返済が厳しい状態は続くことになります。[/aside]個人再生
個人再生は、裁判所を利用して強制的に借金を減額する法的手続きです。任意整理よりも効力が強く、自己破産よりも効力が弱いというのが特徴です。
[aside type=”boader”] 自己破産とは基準や条件が異なり、自己破産の場合、借金の額は無制限ですが個人再生の場合は5000万円未満の借金に限られます。また、個人再生をしても職業の制限をはじめとした自己破産で受ける制限を一切受けることがありませんので、職業制限がネックで自己破産を選択することができない人であっても利用することができるでしょう。[/aside]個人再生は住宅ローンを守り、その他の借金を減額する住宅資金特別条項(住宅ローン特別条項)があります。住宅ローンを守りつつ債務整理をしたいのであれば、個人再生は非常に向いています。
[aside type=”warning”]個人再生は、減額がされても借金を返済しなければなりませんので収入がなければ利用することはできません。また、手続きが自己破産よりも煩雑になるせいで個人的に手続きをおこなうことはあまりおすすめできません。不可能ではありませんが、期限内に定められた必要書類を提出しなければ手続きすべてが無意味になってしまいます。[/aside]仕事の片手間にできるものではありませんので、弁護士へ依頼をすることをおすすめします。弁護士費用は自己破産よりも高額になりますので注意をしましょう。
消滅時効
借金は5年~10年間で消滅時効を迎えます。5年間、借入金の返済を一切せずに、その間、債権者が訴訟や差押えなどを起こさなければ時効により借金の返済義務はなくなります。
しかし、このようにして時効を迎えると、援用時効となり金融事故として記録が残ります。つまり、金融機関から融資を受けたり、クレジットカードを作ったりすることが不可能になるデメリットがあります。
もちろん、時効を迎えることも不可能に近いので、消滅時効を狙い借金の消滅をはかるのは悪手です。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産が不可能であるのならば、任意整理や個人再生で借金の減額とリスケジュールをするのが現実的です。消滅時効を狙うのは非現実的であり、高い確率で失敗するでしょう。[/voice]まとめ
自己破産は、債務整理の中では最後の手段ともいえる法的手続きです。利用をすることで、非免責債権以外の借金はすべて帳消しになります。
しかし、自己破産ができないケースも存在します。
つまり、
- 借金の額がそれほど多くないケース
- 自己破産費用を用意できないケース
- 免責不許可事由が存在するケース
- 自己破産を選択するのが難しい職業についているケース
この4つのケースが考えられます。
借金の額については、3年間で完済することができる額であれば自己破産の申立てをしても認められません。
また、自己破産をするために予納金を裁判所に納める必要がありますが、これが納められないのであれば自己破産の手続きを進めることができません。法テラスの立替金制度などの利用をはじめ、解決する方法は多くありますので、現時点でお金がなくても問題にはなりません。
そして、免責不許可事由が存在する場合ですが相当悪質でないかぎり「裁量免責」にて、自己破産をすることが可能です。
そして、自己破産を選択するのが難しい職業についているケースですが、この場合は仕事を辞めるか別の債務整理の方法である任意整理・個人再生という手段があります。消滅時効を利用する手もありますが、これははっきり言っておすすめできません。
[voice icon=”/wp-content/uploads/concierge_tag.png” name=”concierge” type=”l”]自己破産ができないケースはありますが、まずは弁護士などへ相談をしてできるかできないかを判断してもらいましょう。自分で判断するのは危険です。[/voice]